
まいにち練習4週目を達成したLちゃん姉妹です。
お宝ゲットおめでとう。そしてメダルも4つ✨
シールがずらーっと貼られたカードを見るのはわたしも嬉しいです(*´꒳`*)
継続の力✨わたし以上に、ご本人たちも自分を認める気持ち、誇りに思う気持ちが芽生えてきているのではないかと思います。
うちの教室で頑張ってくれているLちゃん姉妹、本当にありがとう✨
◇◇◇ここから先は、教室の考え配信です。◇◇◇
これから教室を探される方へ、事前に教室の考え方を知っていただきたくて、最近はなるべくこのような記事を書くようにしています。
本日は、自己肯定感と、叱る・ほめるのバランスについて触れていきます。
Lちゃん姉妹のがんばりを見ていると、自己肯定感とはこういう風に作られるものではないかなぁ、と改めて思います。
目標に向かって取り組んだことを、周りの大人が認めてあげるのももちろんですが、まずは自分で認めさせてあげる、そのサポートをしてあげるのが周りの大人の役目ではないかと強く考えます。
できたことは共に喜んだり、
自信を失っていれば元気づけたり、
迷っていたら一緒になって考えたり、
これらが大切なのだと思っています。
その逆で、自己肯定感の言葉の悪用とでも言いましょうか、
最悪なのは、ほめることおだてることしかせず、我が子を有頂天にさせ、天狗にすることです。
昨今の現象かわかりませんが、褒められることは大歓迎だけれど、指摘されることはシャットダウンという子がいます。
自己肯定感という言葉のひとり歩きに注意しなければいけません。
私は、演奏の習得というものは
できていることは→◯、
できていないこと→改善する、
これを繰り返して上達するものだと思っています。
できていないことを自分で受け入れられない子はやはり上達が遅いです。
同学年、同世代の子たちを同時にレッスンしているのでわかるのですが、
そこは本当に顕著なのです。
そして、
弾けない
→面白くない
→面白くないから練習したくない
→練習しないからいつまでも弾けない
→やっぱりつまらない
という悪循環に入り、きっと、結局モノにならず最後は辞める、という結果になってしまうのだと思います。
ピアノは子供時代に数年習ったくらいで形になるようなものではありません。
将来、“2〜3年習った過去”では、ひとりで楽譜をみて楽しめるレベルの趣味にするのは難しいでしょう。
もちろん大半の生徒さんたちはこちらが伝えた通り、自分の課題をきちんと理解し、一生懸命取り組むということができている子たちです。
しかし、上記の負のスパイラルの流れが予想できてしまう生徒さんは、ご本人たちが気づいて改善していく必要があるでしょう。
それをどう本人に気づかせてあげるか、わたしはここにいつも頭を悩ませます。
しかし、週1、30分のピアノレッスンだけではどうにかなるものではなく、
やはり普段の生活から、褒めることと叱ることのバランスを取るように、親の私たちが子供に接して行かなくてはいけないなぁ、とわたしもひとりの親として気付かせられます。
むじかぱれっとは、褒めて叱れる教室でありたいと思っています。
できたこと・上手なことは大袈裟というくらい褒めますが、
ダメな演奏もしっかりと言葉にして伝えていきたいと思います。
誰にでも課題はあるものです。
課題をクリアしてこそ次のステップにあがれる、
また次のステップに乗せてあげるのが私の役目だとも思っています。
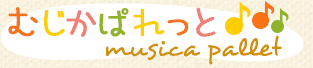



コメント